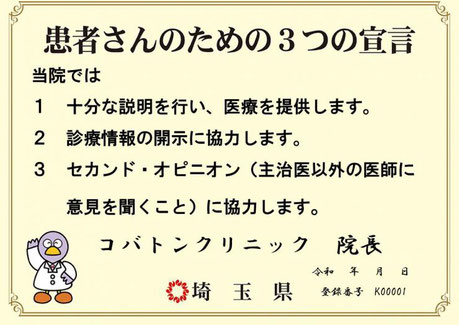在宅医療が広がり、自宅で最期をみとってほしい、みとりたいと考える人が増えている。一方、いざそのときを迎えて、慌てて救急車を呼んでしまう例が多い。救急隊員は、救命処置を続けるか、中止するか、難しい判断を強いられる。専門家は、最期の迎え方については救急車を呼ぶかどうかを話し合って本人の意思を十分に聞き取り、その際の対応、特に医師との連絡方法を確かめておくよう勧めている。
▽8割以上を搬送
総務省消防庁が全国の消防本部を対象にした調査によると、2019~20年の2年間で心肺蘇生を望まない傷病者に対して救急出動した事例は、計約1万900件。発生場所は住宅(53%)、高齢者施設(44%)の二つがほとんどを占めた。
ただ、心肺蘇生をしないという望み通りに進むケースはまれで、8割以上は救急隊による心肺蘇生が続行され、医療機関へ搬送されている。
救急現場で働く医師や看護師、救急隊員らが参加する日本臨床救急医学会は17年、こうした状況での救命のあり方について提言を発表した。
提言によると、到着した救急隊員はまず、心肺蘇生を希望しないことが医師の指示書など書面で示されていたとしても、心肺蘇生など救命処置を開始する。
処置を続けながら、かかりつけ医に連絡を取り、患者の状況を報告し、処置を中止するかどうかを確認する。かかりつけ医に連絡が取れない場合は、消防本部が連携している地域の医師の指示を求める。処置を中止するのは、かかりつけ医が中止の具体的な指示をした場合だ。
これらの原則的な手順を示した上で、提言は、在宅医療の普及状況や各地域の医療の実情に応じて指針を定め、それにのっとって活動するよう促している。
▽現場の難題
この問題で総務省の検討部会委員でもあった救急救命東京研修所の田辺晴山(たなべ・せいざん)教授(救急医学)は「救急隊員の本務として救命は最優先だ。病状や経緯、本人意思など千差万別の状況下で、現場だけで蘇生中止を判断することは極めて難しい」と話す。
命を救うぎりぎりの処置はとても慌ただしい。衣服を脱がして心臓マッサージを施し、電気ショックで心拍再開をさせることも。気管に管を入れたり点滴用の針を刺したりもする。それが本人や家族の意思、心情に沿ったものなのか。医師が蘇生中止を指示した場合も、救急隊員は医師到着前に立ち去っていいのか、判断を求められる。
▽方針決めておく
死亡診断は医師にしかできず、容体が急変したときに自宅でみとるのであれば医師が駆けつけるか、医療機関に運ぶかしかない。ただ、在宅医療には地域によってまだ大きな差があり、全国一律に方針を決めるのは難しい。医療者や救急関係者、行政などが話し合って、地域ごとの事情に応じた救急隊の対応指針が策定されつつある段階だ。
国は、人生の最終段階をどのように迎えるか、患者と家族、医療者、介護者ら関係者が話し合っておく「アドバンス・ケア・プランニング」を推奨し「人生会議」の愛称で普及を図っている。
田辺さんは、どのように対応するかは、あらかじめ医療者と話し合い、家族の間でも食い違いがないように対処方針を決めておくことを勧める。
「救急車を呼んでしまうと、その後どのように進んでも家族に納得いかないケースが生じてしまう。病状や経過、本人の意思をよく知っている在宅医療の医師やかかりつけ医を持ち、ちゃんと連絡が取れるようにしておくことが大切だ」と話している。 (共同=由藤庸二郎)